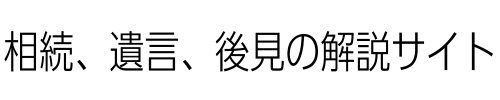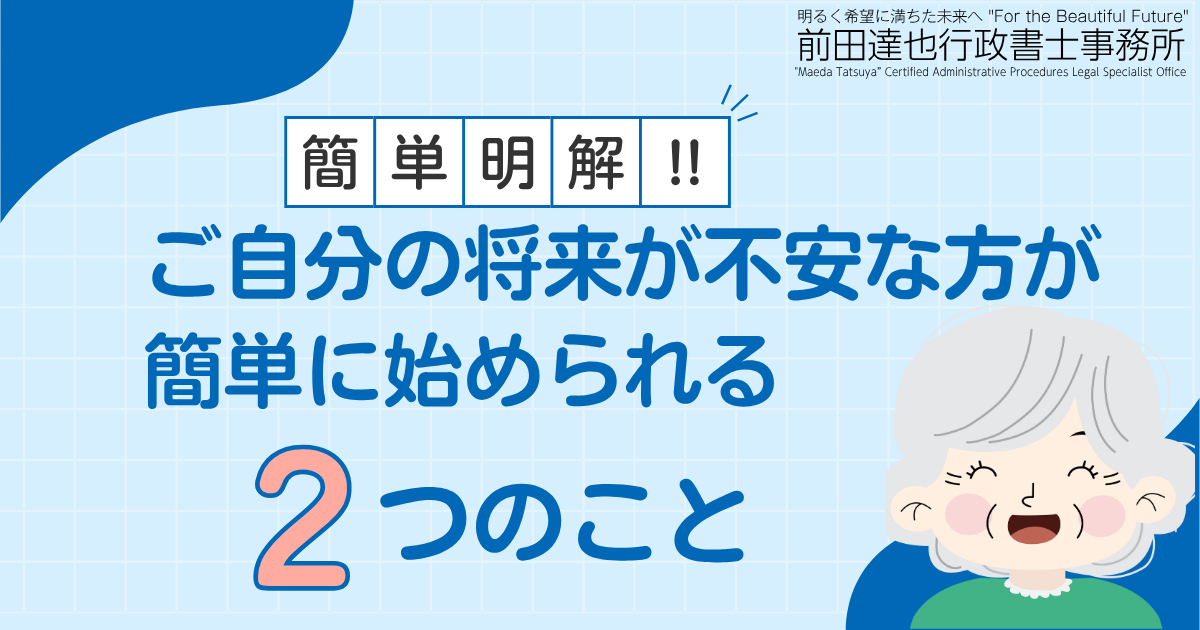誰しもが自分の将来に何らかの不安を抱えていると思います。生計、育児、預貯金、収入、健康、親の介護、年金、自分の介護、、、枚挙にいとまはありません。このブログでは、数ある将来の心配や不安の中から、「自分が亡くなったあとのこと」、「自分に判断能力がなくなったあとのこと」を取り上げます。
自分が亡くなったあとのこと、認知症にかかり判断能力が低下した後のこと、自分のこれからを託すこと、これらは遺言、任意後見、民事信託、死後事務契約など(別のブログで詳しく述べます)により、明確に決めておくことはできます。
しかし、年齢を重ねた方は「遺言書かなきゃ、、、」、おひとりさまは「認知症に備えて誰かにお願いしとかなけりゃ、、、」とお考えにも拘わらず、行動に移されていないのではないでしょうか?これらのことを行動に移すとなると、契約締結、公正証書作成等、自分で簡単にできないこともあり、「いつか、そのうちに、、、」と考えて数年経ち、「まだいいか」となっているのが現実だと拝察します。そのような方にお勧めする二つのことを紹介します。
【市民無料相談会】まずは、市民無料相談会です。定期的な相談会のほか、お祭りや地元のイベントに併せてブースを設定して行っているものなどがあります。予約も要らず、声かけをされた際に少しだけ勇気をもって椅子に座ることで適切なアドバイスを受けることが可能です。もちろん、プライベートは厳格に守られ、その後の勧誘や営業行為なども一切ありません。具体的な問題解決や明確な方針決定はなされませんが、何かのヒントを得られるとても良い機会だと思います。是非、ご活用ください。
【エンディングノート】相談会に遭遇したことがない、知らない人と話すのがおっくうだ、とお考えの方には、エンディングノートがおすすめです。紙とペンがあれば、すぐにでも始められます。わかる範囲で、今書けることだけで良いので、書き出してみることをお勧めします。以下、具体的に書く内容を説明します。
まずは「自分のこと」。氏名、生年月日、住所、本籍、電話番号、メールアドレス、宗教、お世話になっているお寺や教会、その他を書きます。
次に「もしものときの連絡先」。家族、親類、友人、かかりつけ医、など少しでも自分のことを知っている人の名前、連絡先、関係を書き出します。相手の方に了承を得ている必要などまったくありません。
そして、「家族・親族関係」。わかる範囲、わかることだけ書き出してみます。家系図が書ければベストですが、「〇〇△△、父の兄」、「□□※※、姉の夫」など氏名、関係だけでも良いでしょう。
少し難しくなりますが、「所有物、財産」です。土地、家屋の場所、口座、証券、保険、預貯金、負債、自動車などを書きます。
PC・スマホを利用している人は、サイト名、ログイン情報、写真・動画の保存先、住所録、メール・SNSのID、パスワードを書いておくことをお勧めします。《注意》ただし、他人に見られると不正アクセスされる可能性があります。これらを記入したエンディングノートは、厳格に管理する必要があります。
そして、「自分の希望」。もし、「自分が死んだら」あるいは「自分に判断能力がなくなったら」どのようにしてほしいか、を書きます。例えば、自分の介護について決めなければならない場合、誰の意見を尊重してもらうか、どこで介護して欲しいか、介護する人に伝えておきたいことはなにか、などです。
病気やケガの場合に、病名の告知や余命を知らせるか否か、延命治療や終末治療を希望するか、なども書いておくとよいでしょう。
そして、「自分が亡くなった後」です。葬儀をするか、葬儀の規模は、連絡して欲しい人は誰か、どこにどのように埋葬してほしいか、お墓をどうするか、などです。
最後は「伝えたい自分の気持ち、思い出」です。感謝の気持ち、楽しかった思い出、今の思いを書きましょう。
エンディングノートの最大のメリットは、「自分のこと、自分の考えを整理できる」ことだと思います。自分が自分の何を知らないか、自分が「しておいた方が良い」と思うことは何か、などを明らかにすることができます。
エンディングノートに法的な効力は期待できません。しかし、自分のために何かをしてくれる人に手がかりを残すことはできます。手がかりはご自分が思っている以上に重要です。今わかっていること、今決めていること、などの断片的な情報だけでも書いておく価値はあると思います。
エンディングノートの形は自由です。様式が決まっているわけではありません。キレイに製本されたエンディングノートが書店で販売されています。法務省ホームページにも掲載されています。是非、書いてみてください。
ご質問、ご相談があればこちらからどうぞ!